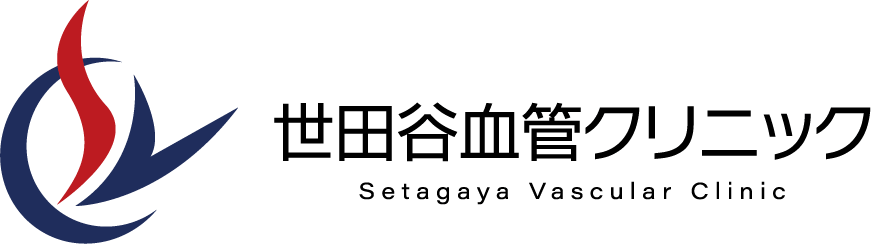下肢静脈瘤の種類
血管には動脈と静脈の2種類があり、下肢静脈瘤は静脈の病気です。
足の静脈の役割は、心臓から足に送られ使い終わった汚れた血液を心臓に戻すことです。重力に逆らって足から心臓に血液を送らないといけないため、静脈の中には“ハ”の字型の弁があり、立っている時に血液が逆流するのを防いでいます。
下肢静脈瘤は、この静脈の弁が壊れることによっておこる静脈独特の病気です。
弁が壊れてきちんと閉まらないために下流の静脈に血液がたまり、静脈がこぶ(瘤)のようにふくれてしまいます。また、汚れた血液が足にたまるため、むくみやだるさなどの症状が起こります。弁が壊れる原因には遺伝や妊娠・出産、長時間の立ち仕事などがあります。まれに湿疹ができたり、皮膚が破れると潰瘍ができ重症になったりすることがあります。
このような方は、できるだけ早くご相談ください。
伏在型静脈瘤
「伏在型静脈瘤(ふくざいがたじょうみゃくりゅう)」とは、下肢(足の部分)に見られる静脈瘤の一種で、特に「伏在静脈」と呼ばれる静脈が拡張したものです。伏在静脈は、脚の皮膚近くを流れる主要な静脈で、血液を心臓に戻す役割を持っていますが、血液の逆流を防ぐための弁が機能しなくなると血流が滞り、静脈が膨らんでこぶ状になることがあります。
原因と症状
【原因】
長時間の立ち仕事、加齢、妊娠、遺伝的要因などが静脈瘤の原因として挙げられます。
【症状】
脚の皮膚の下に浮き出たような膨らみ、むくみ、痛み、重だるさ、かゆみなどが生じることがあります。
側枝型静脈瘤
「側枝型静脈瘤(そくしがたじょうみゃくりゅう)」とは、伏在静脈などの主幹静脈から分岐した側枝(側静脈)が拡張してこぶ状に膨らんだ静脈瘤のことを指します。これは下肢の静脈瘤の一種で、特に脚の表面に近い側枝静脈に血液が滞留し、膨らむことによって発生します。
原因と症状
【原因】
伏在静脈のような主要な静脈で血液の逆流が生じると、その圧力が側枝にも影響を及ぼし、側枝静脈も膨らんで静脈瘤が形成されます。また、加齢、立ち仕事、遺伝的要因なども側枝型静脈瘤のリスクを高めます。
【症状】
脚の皮膚下に見えるコブ状の膨らみ、むくみ、だるさ、痛み、かゆみなどが現れることがあります。放置すると痛みが強くなったり、皮膚炎や潰瘍を引き起こす可能性もあります。側枝型静脈瘤は比較的浅い位置にあるため、硬化療法やレーザー治療が適用されやすく、治療も効果的とされていますが、早期の対応が望ましいです。
網目状静脈瘤
「網目状静脈瘤(あみめじょうじょうみゃくりゅう)」とは、皮膚のすぐ下にある細い静脈が網目状に拡張して浮き出た状態を指します。これは、通常の静脈瘤よりも浅く、太さが1~3ミリ程度の細い静脈で生じることが多く、特に太ももやふくらはぎの外側、膝裏などに現れることが多いです。
原因と症状
【原因】
網目状静脈瘤は静脈の逆流や、血管壁の弱さによって発生します。遺伝、加齢、妊娠、長時間の立ち仕事や座り仕事がリスク要因とされています。
【症状】
青や紫色の網目状の血管が皮膚に浮き出るのが特徴です。通常、痛みや重だるさなどの症状は少ないですが、場合によってはむくみや軽い不快感を伴うことがあります。美容的な観点から治療が希望されることが多いです。網目状静脈瘤は健康上の大きなリスクをもたらすことは少ないものの、美容的な理由や軽度の症状改善のために治療が行われることが一般的です。
クモの巣状静脈瘤
「クモの巣状静脈瘤(くものすじょうじょうみゃくりゅう)」とは、皮膚のすぐ下にある非常に細い静脈が拡張して、クモの巣のような細かい網目状に広がった状態を指します。このタイプの静脈瘤は、赤や青、紫色の細い血管が皮膚の表面に見られることが特徴で、脚や顔、特に太ももや膝の周辺に多く見られます。
原因と症状
【原因】
血管が拡張する原因には、加齢、遺伝、妊娠、長時間の立ち仕事や座り仕事、血液循環の悪化などが関係します。特に女性に多く見られ、ホルモンバランスの変化(妊娠やホルモン治療など)もリスク要因となります。
【症状】
クモの巣状静脈瘤は、通常痛みを伴わないものの、見た目に影響するため美容的な理由で悩まれる方が多いです。稀にかゆみや軽い不快感を感じることもあります。クモの巣状静脈瘤は、一般に健康上のリスクは低いですが、美容的な理由で治療が希望されることが多く、早期治療によって症状の進行を防ぐことも可能です。